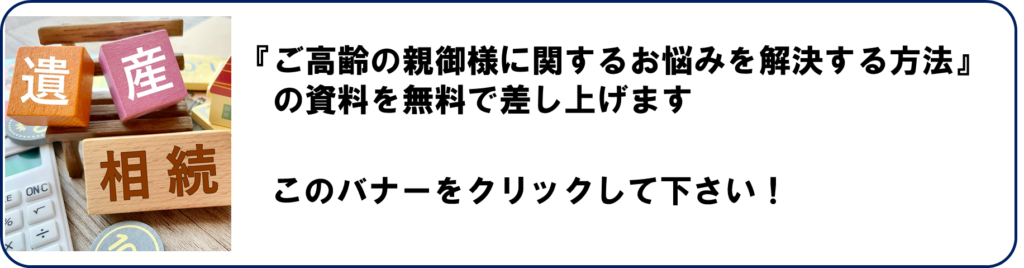相続税とは
相続税とは、人の死亡により財産が移転する場合に、その財産に対して課される国の税金です。
納税義務者と課税範囲
大多数の相続では①に該当しますが、納税義務者とその課税範囲は下表の通り、国籍や住所により詳細に決められています。
| 項番 | 納税義務者の違い | 課税範囲 |
| ① | 相続や遺贈で財産を取得し、取得時に日本国内に住所を有している人 | 取得した全ての財産 |
| ② | 相続や遺贈で財産を取得し、取得時に日本国内に住所を有しておらず、以下に該当する人 ・日本国籍を有し、相続の開始前10年以内に日本に住所を有していた人 ・日本国籍を有し、相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことのない人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く) ・財産取得時に日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人、非居住外国人である場合を除く) | 取得した全ての財産 |
| ③ | 相続や遺贈により日本国内にある財産を取得した人で、財産取得時に日本国内に住所を有しており、①に該当しない人 | 日本国内にある財産 |
| ④ | 相続や遺贈により日本国内にある財産を取得した人で、財産取得時に日本国内に住所を有しておらず、②に該当しない人 | 日本国内にある財産 |
| ⑤ | 上記の①~④に該当せず、贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人 | 相続時精算課税の適用を受ける財産 |
相続税の申告
相続等により取得した財産が、遺産に関する基礎控除額を超える場合には、相続人または受遺者は相続税の申告書の提出を行わなければなりません。逆に言えば、財産の合計額が、基礎控除の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
このとき、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の特例などを適用する前の財産額を計算して、基礎控除額を超えるか否かを判断します。
相続人が2人以上いる場合は、申告書は共同して提出することも可能ですし、それぞれ単独で提出することも可能です。
提出先は、親御様(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。
相続税の申告は、原則として、親御様(被相続人)の死亡を知った日の翌日から10ケ月以内に行うことになっています。期限までに申告を行わない場合、無申告加算税が課されることがあります。
この期限日が、土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その次の開庁日が期限日になります。
相続税の納付
申告書提出と、相続税の納付は、期限が同じになりますので注意が必要です。
親御様(被相続人)の死亡を知った日の翌日から10ケ月目となる日までに、申告書の提出だけでなく、税金の納付も済ませる必要があります。納付期限を過ぎてしまうと、罰則として延滞税がかかってきます。
相続税の納付方法としては、金融機関での納付のほか、クレジットカード、コンビニエンスストア、税務署の窓口での支払いも選択可能となっています。基本的に現預金で支払うことが前提になっています。
しかし実際は、相続税は高額となる場合が多いですから、金融機関で納付することが一般的です。税務署備え付けの納付書を利用します。
相続税は一括納付が原則ですので、1部をクレジットカードで納付し、残りを金融機関で納付するといったことは出来ません。
また、相続人が複数名いる場合には、相続人はそれぞれ個別に納付することをお勧めします。
代表者がまとめて納付することにより手間が省けるように思えますが、立替分が贈与とみなされる場合もありますので、まとめての納付は避けた方が無難です。
遺産の大部分が不動産で、現預金が少ない場合など、現金での相続税納付が困難な場合があります。
こうした場合の救済策として、延納制度や物納制度があります。
・延納制度:何年かに分けて相続税を納付する制度
・物納制度:相続税で取得した財産そのもので納付する制度
これらの制度を利用するには、申告書の提出期限までに、税務署長の許可を受ける必要があります。
ただし、これらの制度利用は申請すれば単純に許可される性格のものではありませんから、否認された場合は他の手段がとれるように、時間的な余裕を持った申請を心がけてください。
この記事は、ここまでになります。
※この記事は「相続税とは」に続きます。